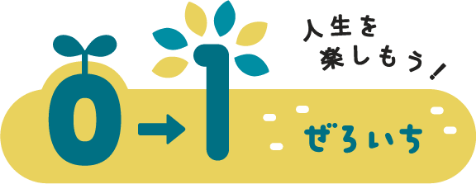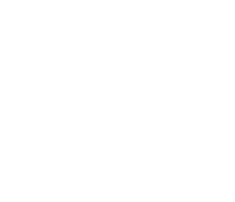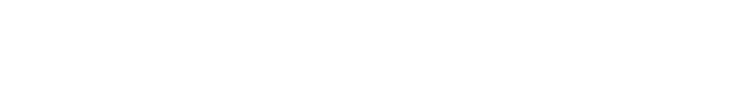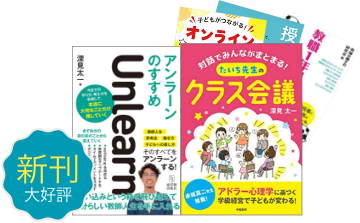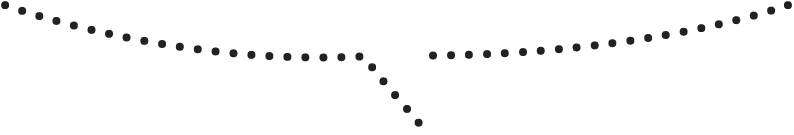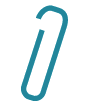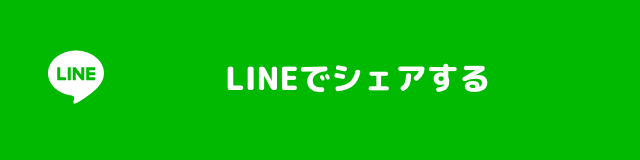クラス会議
2025/5/12
教室が変わる!2年目教師のための「課題の分離」実践法 〜アドラー心理学を学級経営に生かす〜

「もっと子どもたちに言うことを聞いてほしい」「やる気がない子にどう接したらいいか分からない」──そんな悩みを抱えている2年目の先生へ。実は、アドラー心理学における「課題の分離」を実践することで、驚くほど学級が安定し、自分の気持ちも軽くなります。
■ 課題の分離とは?
アドラー心理学では、すべての問題行動や選択には「その人自身の課題」があると考えます。そして、他人の課題に無理に介入しようとすると、関係がこじれたり、無力感を覚えたりするのです。
「課題の分離」とは、自分の課題と他人の課題を明確に分けて考えること。たとえば「宿題をやるかどうか」は子どもの課題。「やらせなきゃ」と教師が背負いすぎると、お互いに疲弊してしまいます。
■ 教室での実践方法3ステップ
- 「誰の課題か?」を冷静に見極める
まず、日々のやりとりの中で「これは本当に自分の責任か?」と立ち止まって考えてみましょう。朝の支度が遅い子、忘れ物が多い子、ノートを丁寧に書かない子…。それは「その子自身の学びに関する課題」であり、あなたの責任ではありません。先生が代わりにやってあげたり、過度に口出しすると、自立の機会を奪ってしまいます。 - 課題を返す勇気を持つ
たとえば「提出物を出さない子」がいたとします。ここで怒ったり、毎日声かけしたりする代わりに、「出すのはあなたの判断だよ。でも、提出しないとどうなるかは自分で考えてね」と静かに伝える。こうした対応は、子どもに自分の行動に責任を持たせる一歩となります。 - 信頼のメッセージを添える
「課題の分離」は冷たく突き放すことではありません。大切なのは、“見守る覚悟”と“信頼のまなざし”です。「あなたならできると信じている」「困ったらいつでも相談してね」という姿勢を持って、子どもたちの選択を尊重することが、かえって信頼関係を深めるのです。
■ 教師自身の心も安定する
課題を自分で抱え込まないことで、先生自身のストレスもぐっと減ります。「私がなんとかしなきゃ」と思わなくてもいいと気づけるだけで、毎日の学級経営が軽やかになります。
もちろん、すぐにすべての課題を切り離すのは難しいかもしれません。でも、「これは誰の課題だろう?」と自問する習慣を持つことが、アドラー流の学級づくりの第一歩になります。
2年目の今だからこそ、「すべてを背負わない勇気」を持つことが、教師としての成長につながります。「課題の分離」という視点を取り入れて、もっと自分らしい学級経営を目指してみませんか?
こんな記事も読まれています↓↓↓