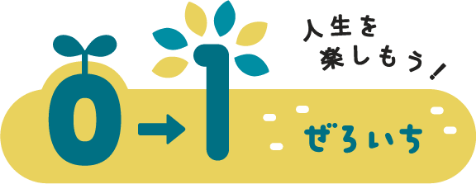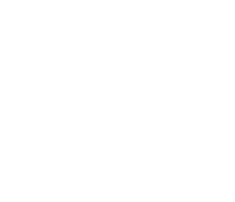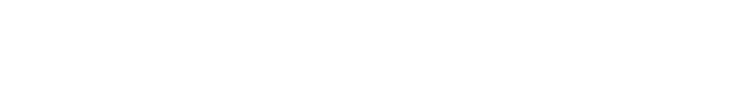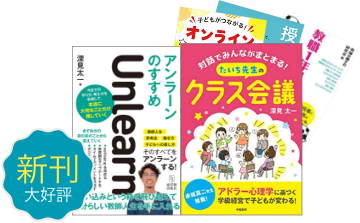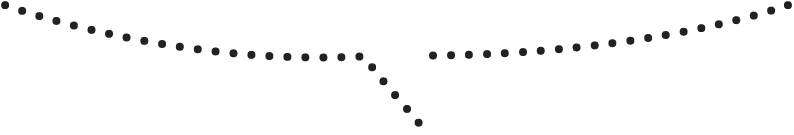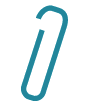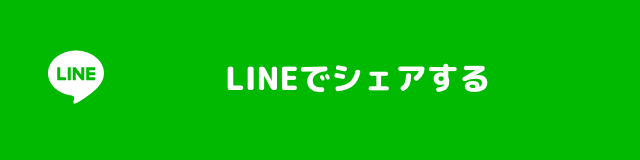クラス会議
2025/5/11
2年目教師のための学級経営術 〜アドラー心理学でクラスを安定させる〜

小学校教員2年目。
少し余裕が出てきた反面、「去年よりうまくいかない…」と感じる先生も多いのではないでしょうか。実は、学級経営においては2年目が大きなターニングポイント。そこで今回は、アドラー心理学をベースにした“安定した学級づくり”のヒントをご紹介します。
■ アドラー心理学とは?
アドラー心理学の中心にあるのは、「人はつながりの中で生きる存在である」という考え方です。子どもたちもまた、「自分はこのクラスにとって大切な存在だ」と感じられることで、落ち着きや安心感を得て行動が安定していきます。アドラーが大切にした「共同体感覚(=所属感と貢献感)」を育てることが、学級経営の土台となるのです。
■ クラスを安定させる3つのステップ
- 安心できる人間関係をつくる
最初のステップは「心理的安全」の確保です。叱る前に、まず聴く姿勢を。失敗しても認められる空気、意見を言っても否定されない関係性ができているかを見直しましょう。朝の会で「最近うれしかったこと」などを話す時間を設けると、互いを理解し合うきっかけになります。 - 子どもの「目的」に注目する
アドラー心理学では、問題行動の裏には「目的」があると考えます。たとえば授業中に騒ぐ子がいたとき、「注目されたい」「仲間に入りたい」といった動機があるかもしれません。その行動をただ叱るのではなく、「その子が本当に求めているものは何か?」という視点で関わると、対話の質が変わります。 - 子どもを「仲間」にするクラス会議の活用
クラスの中で問題が起きたら、大人が解決するのではなく、子どもたちと一緒に考える機会をつくりましょう。週1回のクラス会議を通して、「このクラスをもっとよくするには?」をテーマに子ども同士が話し合うことで、所属感と責任感が育ちます。特に、自分のアイデアが採用される体験は、子どもにとって大きな自信となります。
■ 教師も完璧でなくていい
最後に大切なのは、「教師自身も人間である」と自覚することです。失敗したときは素直に子どもに謝ることも、信頼関係を築くうえでとても効果的です。アドラー心理学では「対等な人間関係」を大切にします。上から指導するのではなく、同じ目線で歩むパートナーとして子どもと関わることで、学級は確実に安定していきます。
2年目の不安や葛藤は、成長のチャンスでもあります。アドラー心理学をヒントに、「安心して学べるクラスづくり」を少しずつ積み上げていきましょう。教師としての自信も、クラスの信頼も、そこからきっと育っていきます。