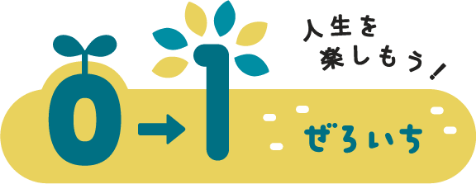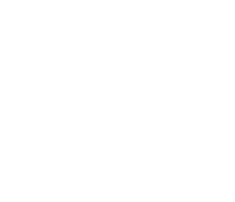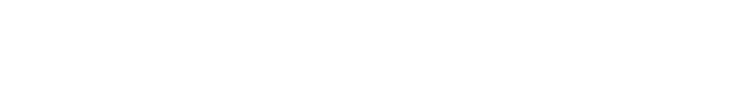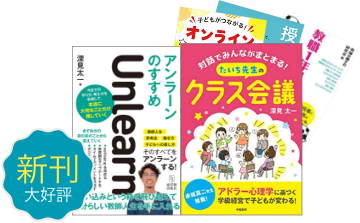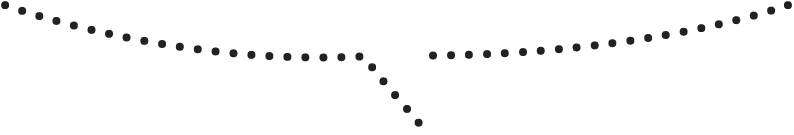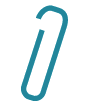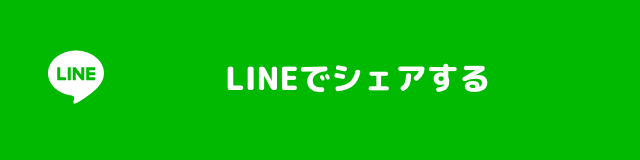クラス会議
2025/5/13
自己決定が子どもを変える!〜2年目教師のためのアドラー心理学×学級経営術〜
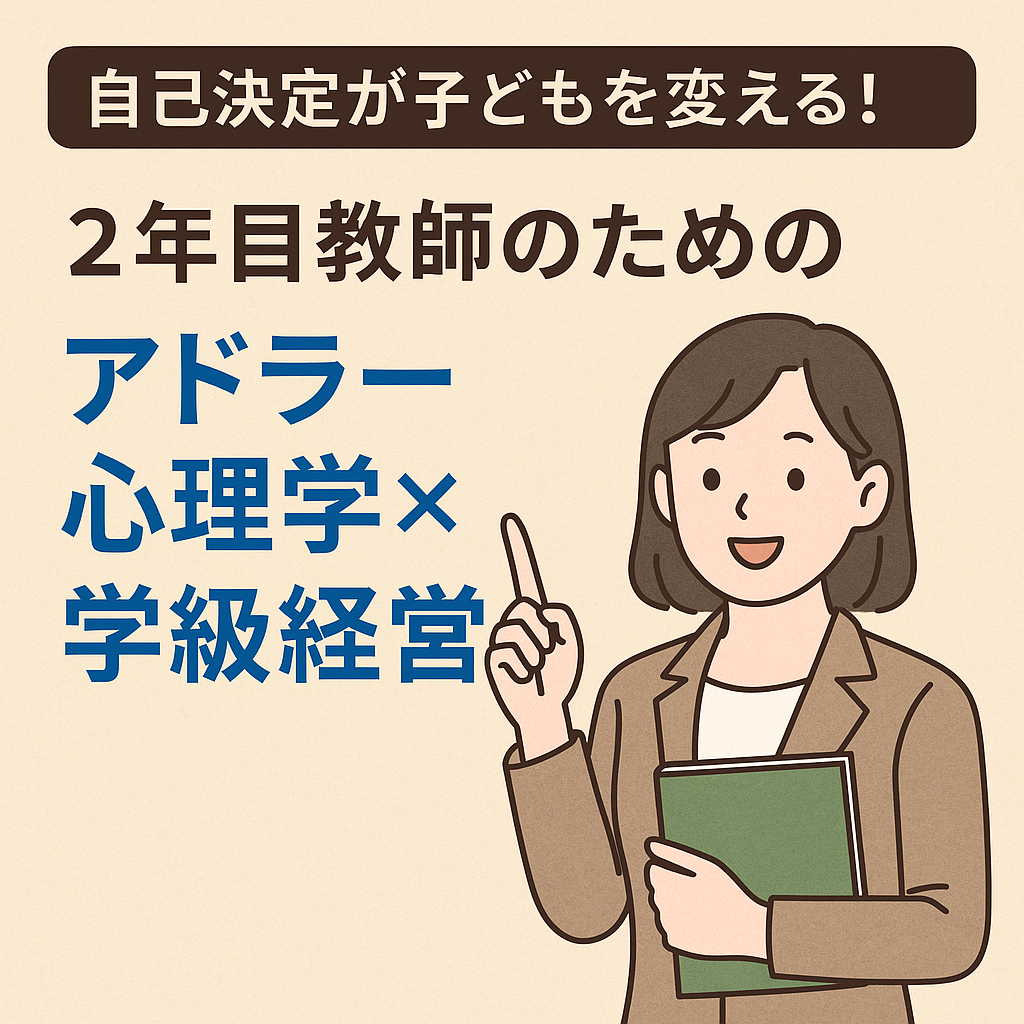
2年目の教師として迎える新学期。「昨年よりうまくやりたい」「もっとクラスを安定させたい」——そう願う先生も多いはずです。でも、どうしたら子どもたちが落ち着き、自分から行動してくれるようになるのでしょうか?
そこで注目したいのが、**アドラー心理学の「自己決定感」**です。
■ 自己決定とは何か?
アドラー心理学では、「すべての行動は本人の目的に基づく選択である」と考えます。つまり、人は誰かに命令されて動くよりも、自分で決めたことに責任を持ち、より主体的に行動するのです。
学級経営でもこれは同じ。教師がルールを一方的に押しつけるのではなく、子ども自身が「選ぶ」体験を積み重ねることが、安定したクラスづくりへの第一歩になります。
■ 学級を安定させる3つの自己決定ポイント
- ルールを子どもたちと一緒に作る
「廊下は静かに歩きましょう」といったルールも、教師が決めるのではなく、子どもたちと話し合って決めることで、納得感が生まれます。たとえば学級会で、「教室で快適に過ごすにはどんなルールが必要か?」をテーマに話し合いをしてみましょう。自分たちで決めたルールには、自然と責任感を持つようになります。
- 日常の中に選択肢を用意する
日直の仕事、係活動、給食の配膳の順番…。日々の細かい場面にも「選べる」余地を残しましょう。「どちらがいい?」と聞くだけでも、子どもは自分で考え始めます。教師がすべてを決めてしまうのではなく、小さな選択の積み重ねが、自立と安定を支えます。
- 失敗も自分で引き受ける経験をさせる
アドラー心理学では、「失敗をどう乗り越えるか」こそが成長のチャンスとされます。忘れ物をしたとき、友だちとトラブルになったときも、すぐに大人が介入するのではなく、「どうしたらよかったと思う?」「次はどうしたい?」と問いかけ、自分の行動を振り返る機会にしましょう。
■ 教師は「信頼して任せる」存在に
子どもが自分で選び、自分で行動するためには、「先生は私の力を信じてくれている」という安心感が必要です。教師の仕事は、すべてを管理することではなく、「見守り、支えること」。完璧にコントロールしようとするのではなく、信頼をベースにした関係性を築くことが、自己決定を支える鍵になります。
こんな記事も読まれています↓↓↓