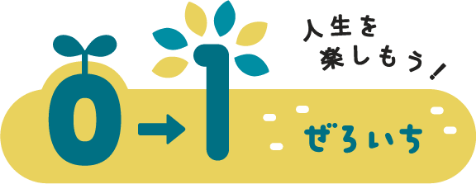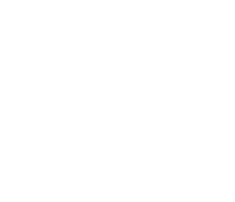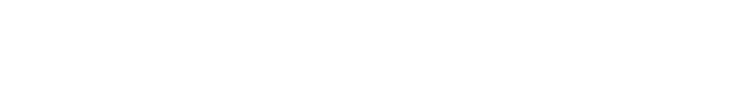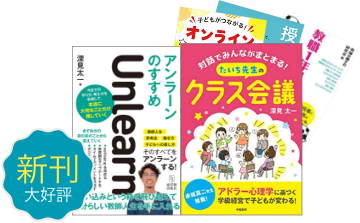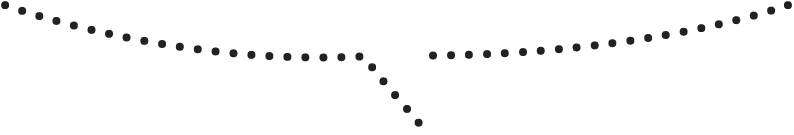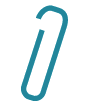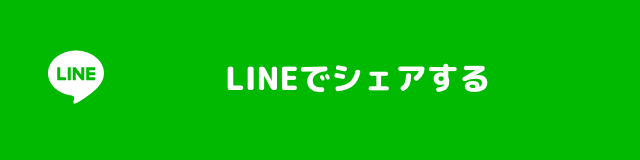クラス会議
2025/5/14
「他者貢献感」が学級を変える!2年目教師のためのアドラー心理学的学級経営
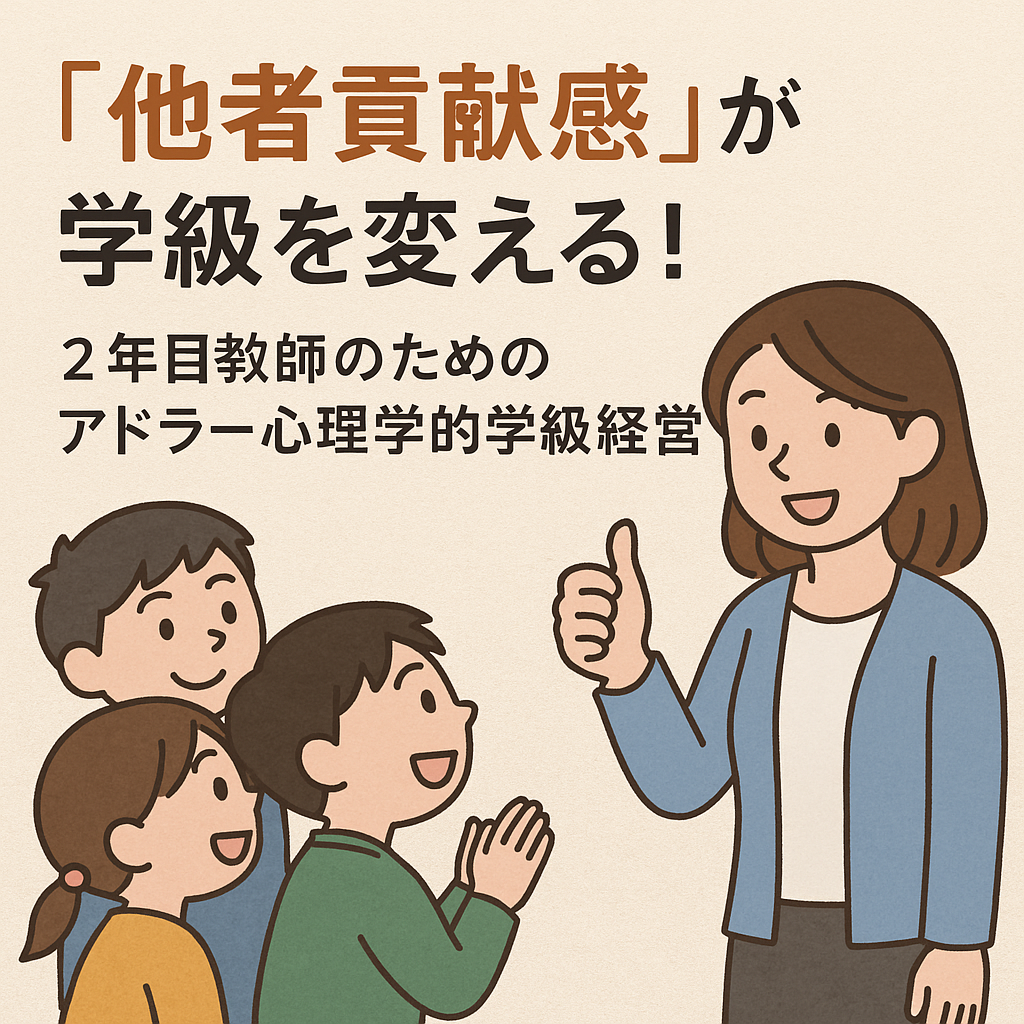
2年目の小学校教員にとって、学級を安定させることは大きな課題です。1年目は目の前のことに必死だったけれど、少し余裕が出てきた今、「もっとクラスを良くしたい」と感じていませんか?その想いを実現するためのカギが、アドラー心理学における「他者貢献感」という考え方にあります。
■ アドラー心理学とは?
アドラー心理学では、人間の幸福は「所属感」と「貢献感」によって高まると考えます。つまり、「自分はこの場に必要とされている」「誰かの役に立てている」と感じられることが、安心感や自信の源になるのです。
これは子どもたちにとっても同じ。学級が安定するためには、子ども一人ひとりが“自分もこのクラスに貢献できている”と実感できることが重要です。これが「他者貢献感」です。
■ 学級を安定させる3つの実践ポイント
- 「ありがとう」を循環させる環境づくり
「ありがとう」が自然に飛び交うクラスは、貢献感が育つ場です。係活動や当番の仕事が終わったとき、「〇〇さん、ありがとう」と言い合う文化をつくりましょう。教師自身が意識して感謝を伝えることも大切です。子どもたちは、自分の存在が誰かの役に立っていると感じたとき、心から落ち着いて行動できるようになります。
- 一人ひとりの役割を見える化する
どんな小さなことでも「自分の役割がある」と思えることが、他者貢献感につながります。例えば、掃除当番だけでなく「本棚の整理係」や「朝の挨拶係」など、細かな係を設けてみましょう。誰にでも出番がある状態をつくることがポイントです。
- クラス会議で“貢献できる自分”を実感させる
週1回のクラス会議を取り入れ、「このクラスをもっと良くするには?」というテーマで話し合う場を設けましょう。「アイディアを出すこと」「誰かの意見に賛成すること」「司会進行を務めること」など、どんな形でも貢献できるように仕組みを工夫することが重要です。
■ 他者貢献感が学級にもたらすもの
他者貢献感が高まると、子ども同士が互いに認め合い、助け合う空気が生まれます。問題行動も減り、いじめや孤立も起きにくくなります。教師が一人で「学級をまとめよう」とするのではなく、クラス全体で支え合う文化を育てることが、学級の安定には欠かせません。
2年目の先生にとって、子どもたちが安定して過ごせるクラスをつくることは、自身の成長にもつながります。アドラー心理学の「他者貢献感」を軸にした学級経営そしてクラス会議を、ぜひ今日から取り入れてみてください。